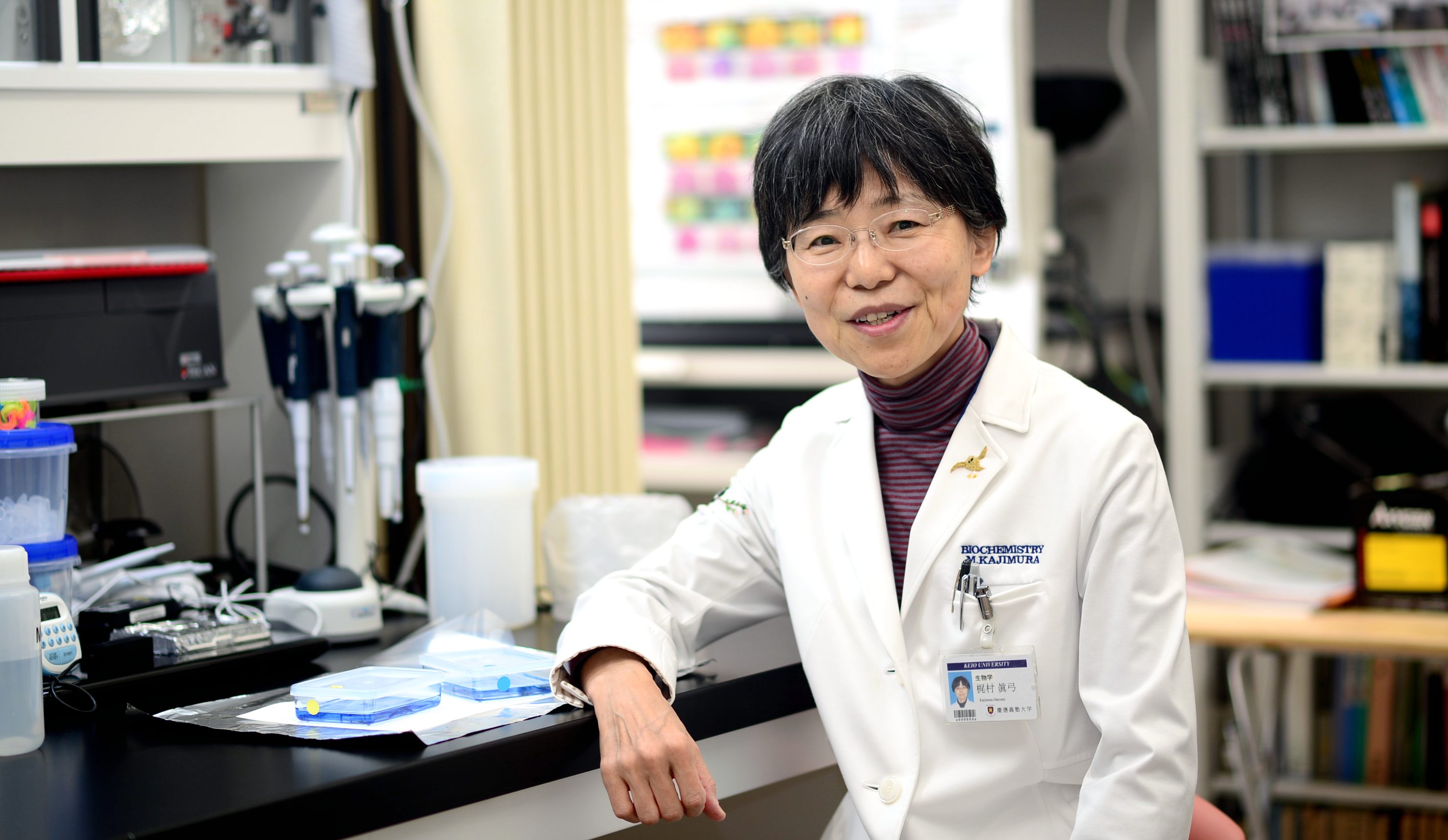ジャンル 現代社会と科学
中野校
神経細胞のはたらきと認知症
梶村 眞弓(早稲田大学客員教授)

| 曜日 | 木曜日 |
|---|---|
| 時間 | 10:40~12:10 |
| 日程 |
全4回
・08月21日 ~
09月11日 (日程詳細) 08/21, 08/28, 09/04, 09/11 |
| コード | 320712 |
| 定員 | 36名 |
| 単位数 | 1 |
| 会員価格 | 受講料 ¥ 11,880 |
| ビジター価格 | 受講料 ¥ 13,662 |
講義概要
私たちの思考・記憶・行動などを司る脳の機能を基底するのは「神経細胞(ニューロン)」とよばれる高度に分化した細胞群です。ニューロンのおかげで、正常な行動をとることができます。人生100年時代を迎えた今、脳の老化を防ぐこと、認知機能を維持することは、誰もの願いであることでしょう。さて、脳の機能と生活習慣(運動、睡眠、食事)は、科学的にどのようにリンクしているのでしょうか。まずは、神経細胞の構造と機能を学ぶことから始めましょう。そして、「認知症」で起こる神経細胞の不具合の真相へと学びを発展させて参りましょう。本講座が、衰え知らずの脳と良い生活習慣の接点を考える機会になれば幸いです。
※2024年度秋講座と重複する部分があります。
各回の講義予定
| 回 | 日程 | 講座内容 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 08/21 | 中枢神経系を知ろう | 「中枢神経系」は、「脳」とそれに続く「脊髄」で構成されています。脳には灰白色の「灰白質」と、白色の「白質」という部分があります。「灰白質」は、脳の「表土」の部分にあたり、密につまった神経細胞の細胞体の集まりです。この場所で「精神の計算活動」が行われ、記憶が貯蔵されます。その下には、ヒトの脳の約半分を占める「白質」と呼ばれる「岩盤」があります。白質は、「何百万本もの通信ケーブル」からできていて、長いものは1メートルにも及びます。「百聞は一見に如かず」鶏の脊髄を材料として、「灰白質」と「白質」を観察してみましょう |
| 2 | 08/28 | 神経細胞の特徴を知ろう 〜マクロからミクロへ〜 | 神経系において情報を集め、演算し、伝え、処理するのは、神経細胞(ニューロン)です。神経細胞は、細胞体とそこから延びる突起からできています。例えば、私たちの運動神経の突起の中には、1メートルにも及ぶものもあり、ミクロの細胞の観点からはとてつもなく長いのです。この突起は「軸索」と呼ばれ、その中には「モータータンパク質」という驚くべきミクロの軸索輸送システムが存在します。大活躍するモータータンパク質の様子を動画で紹介します。 |
| 3 | 09/04 | Aging Brainその1 〜脳が衰えるって?〜 | 正常な神経細胞のはたらきを維持できなくなると、様々な不具合が生じます。「神経変性疾患」とひとくくりで呼ばれる病態で、一体どんな変化・現象が起こっているかを一緒に学びましょう。 |
| 4 | 09/11 | Aging Brainその2 〜良い生活習慣と衰え知らずの脳の関係とは?〜 | 加齢による認知機能低下の速さと程度には個人差があります。多くの人は、認知機能が徐々に減退することを経験します。一方で、まれに生涯認知能力を維持できる人が存在します。何が異なるのでしょうか。現時点で示唆されている要因について、一緒に学びましょう。 |
ご受講に際して(持物、注意事項)
◆本講座の内容は、2024年度秋講座(10月に実施)「中枢神経系をみてみよう」と重複する部分がありますのでご留意ください。
講師紹介
- 梶村 眞弓
- 早稲田大学客員教授
- 1995年、カリフォルニア大学デイヴィス校生理医学系博士課程修了。大西洋を渡り、ロンドン・インペリアルカレッジ医学部で研鑽。1999年、慶應義塾大学医学部医化学教室で日本でのキャリアをスタート。脳梗塞後遺症を軽減したいという思いのもと、一貫して分子レベルで病態を解明することに傾注してきた。ATPというエネルギー分子が、脳梗塞巣で枯渇していく様子を可視化することに世界で初めて成功した。2021年、慶應義塾大学・医学教育貢献賞を受賞。2022年3月、慶應義塾大学 医学部教授職を定年退職。現在、早稲田大学研究院ナノ・ライフ創新研究機構 規範科学総合研究所 客員教授(客員上級研究員)