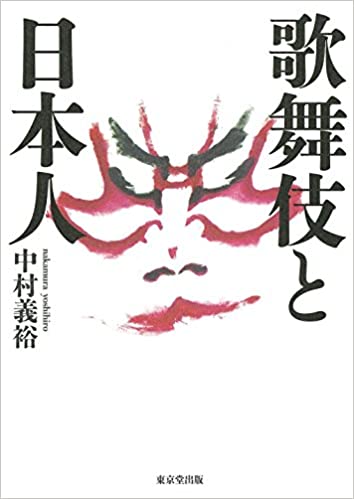ジャンル 芸術の世界
中野校
オトナの歌舞伎入門―はじめてでも深く楽しむ 11年目のファイナル・イヤー!
中村 義裕(演劇評論家、劇作・演出家、日本文化研究家)

| 曜日 | 月曜日 |
|---|---|
| 時間 | 15:05~16:35 |
| 日程 |
全6回
・04月07日 ~
05月26日 (日程詳細) 04/07, 04/14, 04/21, 05/12, 05/19, 05/26 |
| コード | 310402 |
| 定員 | 24名 |
| 単位数 | 1 |
| 会員価格 | 受講料 ¥ 17,820 |
| ビジター価格 | 受講料 ¥ 20,493 |
目標
・歌舞伎の魅力を体系的に、映像や音声を多用し、身近に理解する。
・「今の歌舞伎」の演目・俳優などを取り上げ、初心者には鑑賞の手引きともなる。
・他では聴けない話などの話題も織り込み、多面的な講義とする。
講義概要
今、世代交替の最中にある「歌舞伎」を、時系列、横断的など多角的な観点から解説する。初心者には、敷居が低い歌舞伎への入門講座として、観劇経験者には知識の整理として、歌舞伎観劇の経験に関係なく、楽しめる講義を行う。「難しいことは簡単に、簡単なことは楽しく」話すことをモットーに、2014年以来続けてきた講座の「ファイナル・イヤー」とする。そのため、すべて「初めての話題」とし、過去の受講者にも新鮮な話題を提供する。6回の講義で、歌舞伎に関する一通りの知識の習得+αを目指す。最終回は、受講生の「知りたいこと」に焦点を当てた講義としたい。そのため、第一回より質問を受け付ける。
各回の講義予定
| 回 | 日程 | 講座内容 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 04/07 | 「尾上菊五郎襲名から観る尾上菊五郎家(音羽屋)の芸」 | 5月の歌舞伎座公演から、八代目尾上菊五郎の襲名興行が行われる。しかし、これは今までの歌舞伎界にはなかった方式である。「尾上菊五郎家」は、今までの歌舞伎界でどのような役割を果たしてきた家なのか、を併せて検証する。 |
| 2 | 04/14 | 「今の歌舞伎は危機なのか? 過去の経験を踏まえて語る」 | 時代と歌舞伎の関係が激しく変わる中、現在の歌舞伎は「危機」なのだろうか? 何が問題になっているのか。過去にはどんな危機があり、それをどう乗り越えたのか。今までにない側面から、歌舞伎の歴史を眺める。 |
| 3 | 04/21 | 「十三代目市川團十郎白猿と十代目松本幸四郎」 | 今後の歌舞伎界の中心に立つべき二人の人気俳優。しかし、見ている方向は全く違っている。二人は何を目指し、歌舞伎とどう対峙するつもりなのか。市川家と松本家の関係は?映像を交え、検証と今後の展開を語る。 |
| 4 | 05/12 | 「中村義裕セレクションの歌舞伎名作。ベスト5」 | 50年を超える歌舞伎観劇歴の中で、作品として優れているベスト5を紹介し、その見どころやツボを紹介する。今後の観劇の手引きとして参考にされたい。 |
| 5 | 05/19 | 「上方和事」の色気を味わう | 秘蔵映像をもとに、「上方和事」の代表的な演目、『吉田屋』、『心中天網島』、『曽根崎心中』などの世界を堪能する。 |
| 6 | 05/26 | 「何でも答える90分と芸の話」 | 第一回の講義から、受講者には無記名で「質問」を集め、最終回でその疑問に回答する。その場の質問でも可。また、それらの質問を通して見える「歌舞伎の芸」の真髄を語る。 |
ご受講に際して(持物、注意事項)
◆休講が発生した場合の補講日は、6月2日(月)に予定しています。
◆第一回より質問を受け付けますので、筆記用具をお持ちください。
講師紹介
- 中村 義裕
- 演劇評論家、劇作・演出家、日本文化研究家
- 1962年東京生まれ、早稲田大学第二文学部演劇専修卒業。主な著書に『九代目 松本幸四郎』(2014年、三月書房)、『日本の伝統文化しきたり事典』(2014年、柏書房)、『歌舞伎と日本人』(2018年、東京堂出版)、『明治・大正・昭和・平成 芸能史事典』(2019年、東京堂出版)、『平成演劇史事典』など。ウェブサイト「演劇批評」で多彩なジャンルの演劇批評を展開。最近は日本の伝統文化にも研究の幅を広げ、新たな視点での執筆や講演多数。