ジャンル 人間の探求
オンライン
「弁証法」なんてあるのか?その常識を問い直す!
岡本 裕一朗(玉川大学名誉教授)
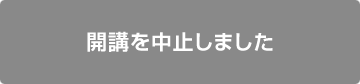
| 曜日 | 水曜日 |
|---|---|
| 時間 | 19:00~20:30 |
| 日程 |
全5回
・01月29日 ~
02月26日 (日程詳細) 01/29, 02/05, 02/12, 02/19, 02/26 |
| コード | 740567 |
| 定員 | 30名 |
| 単位数 | 1 |
| 会員価格 | 受講料 ¥ 14,850 |
| ビジター価格 | 受講料 ¥ 17,077 |
目標
・哲学の基本的な考え、ものの見方を理解する。
・社会が大きく転換するとき、哲学がどう変わるのかを理解する。
・社会的な教養として、哲学の歴史を知る。
講義概要
哲学の中で、「弁証法」という概念は、ドイツの哲学者ヘーゲルの名とともに、一般的によく知られています。とくに、「正―反―合」の合言葉によって、役に立つ方法として高校の教科書にもしばしば掲載されるほどです。ところが、「正―反―合」の「弁証法」をヘーゲルが主張したことはなく、いわば都市伝説のようなものです。この講座では、「弁証法」の歴史的な原義であるギリシア語の「ディアレクティケー」にさかのぼって、プラトンやアリストテレスからはじまり、中世での「自由七科」、そしてカントやヘーゲル、そしてその後のマルクス主義者たちの意味の転用についてお話します。この機会にぜひ、哲学の常識を疑ってみましょう。
各回の講義予定
| 回 | 日程 | 講座内容 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 01/29 | ヘーゲルは「正―反―合」の「弁証法」を唱えたのか? | 「弁証法」といえばヘーゲルという誤解を糺します! |
| 2 | 02/05 | プラトンが始めた「問答法=ディアレクティケー」 | 「ディアレクティケー(問答法)」は、プラトンが命名した哲学の方法 |
| 3 | 02/12 | アリストテレスの「弁証術(ディアレクティケー)」 | 「ディアレクティケー」は、議論を訓練する方法となる |
| 4 | 02/19 | 中世の自由七科の「ディアレクティカ」からカントの「弁証論」まで | 哲学の歴史の中で、「ディアレクティケー」はどう変容したのか? |
| 5 | 02/26 | マルクスとエンゲルスの「弁証法」 | 「弁証法」のドグマを形成したマルクス主義の考えを検討します |
ご受講に際して(持物、注意事項)
◆哲学について予備知識がなくても受講可能です。
◆社会常識として、哲学を学びたい人も歓迎します。
◆休講が発生した場合の補講は、3月5日(水)を予定しております。
◆Zoomウェビナーを使用したオンライン講座です。
◆お申込みの前に必ず「オンラインでのご受講にあたって」をご確認ください。
◆本講座の動画は、当該講座実施の翌々日(休業日を除く)17:30までに公開します。インターネット上で1週間のご視聴が可能です。視聴方法は、以下をご確認ください。
【会員】授業動画の視聴方法(会員向け)
【ビジター・法人会員】授業動画の視聴方法(ビジター・法人会員向け)
講師紹介
- 岡本 裕一朗
- 玉川大学名誉教授
- 1954年福岡生まれ。九州大学大学院文学研究科博士課程単位取得満期退学。博士(文学・九州大学)。九州大学文学部助手、玉川大学文学部教授などを経て、玉川大学名誉教授。専門分野は西洋近現代哲学。著書に『ヘーゲルと現代思想の臨界』(ナカニシヤ出版)、『フランス現代思想史』(中公新書)、『いま世界の哲学者が考えていること』(朝日新聞出版)、『哲学と人類』(文藝春秋社)、『哲学100の基本』(東洋経済新報社)などがある。





