ジャンル 世界を知る
早稲田校
イギリス喫茶の歴史―コーヒーから紅茶の国へ
齊藤 貴子(早稲田大学・上智大学大学院講師)
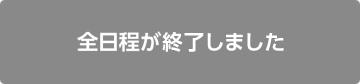
| 曜日 | 火曜日 |
|---|---|
| 時間 | 15:05~16:35 |
| 日程 |
全10回
・10月01日 ~
12月03日 (日程詳細) 10/01, 10/08, 10/15, 10/22, 10/29, 11/05, 11/12, 11/19, 11/26, 12/03 |
| コード | 130306 |
| 定員 | 30名 |
| 単位数 | 2 |
| 会員価格 | 受講料 ¥ 29,700 |
| ビジター価格 | 受講料 ¥ 34,155 |
目標
・イギリスの歴史文化を広く深く学ぶ。
・コーヒーを原点とし、紅茶によって形づくられたイギリスの喫茶や社交文化について理解を深める。
・イギリスの「近代」においてコーヒーと紅茶が果たした多大な役割、その功と罪を、歴史的観点はもちろん芸術的観点からも考察する。
講義概要
イギリスといえば「紅茶の国」。しかしながら、喫茶および社交面でのイギリス近代文化の幕開けをもたらしたのは、実は紅茶ではなくコーヒーというのが、ひとつの歴史的事実ではあります。そのコーヒーをやがて紅茶が凌駕し、イギリスが「紅茶の国」となっていった経緯は、国家そのものの近代化ないし帝国化の一側面だったといっても過言ではありません。知る人ぞ知るこの歴史的事実を、コーヒーや紅茶そのものの魅力はもちろん、21世紀現時点でのカフェ文化事情や芸術的な観点からも多角的に考察し、イギリス歴史文化への理解を深めてまいります。
各回の講義予定
| 回 | 日程 | 講座内容 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10/01 | イントロダクション:コーヒーと紅茶にとっての21世紀 | コーヒーと紅茶は永遠のライバル関係。21世紀現在において、イギリス喫茶界をリードしているのはコーヒーという説もありますが、少なくとも二者間のパワーバランスは実に微妙であり、その時どきの世界情勢によっても常に変動を余儀なくされているというのが実情ではないでしょうか。この前提にのっとり、イギリスにおけるコーヒーと紅茶の歴史を紐解くうえで欠かせないものとして、まずは21世紀の喫茶シーンの新たな潮流に目配りすることから本講座をはじめてみたいと思います。 |
| 2 | 10/08 | 紅茶ではなくコーヒーの国だった?イギリス | 紅茶よりコーヒーのほうが一足はやく17世紀のイギリスにもたらされたことは、様々な研究の成果により、すでに多くの人が知る事実となって久しい感があります。しかしそうであったからこそ、紅茶もまたコーヒーに続いて次第に飲まれるようになった経緯は、あまり知られていないかもしれません。実はコーヒーがあったからこそ紅茶がある……イギリス喫茶の歴史におけるその動かしがたい事実をご紹介してまいります。 |
| 3 | 10/15 | 喫茶と社交の場「コーヒーハウス」の誕生① | イギリスにおける喫茶店の元祖「コーヒーハウス」の登場は、ひとつの歴史的事件。少なくとも、その登場以前と以後とでは社会の様相がガラリと異なる、歴史を画する流行事情であったとはいえるでしょう。まずは、イスラム圏に端を発するコーヒーハウスがイギリスに受容されていった経緯をご紹介します。 |
| 4 | 10/22 | 喫茶と社交の場「コーヒーハウス」の誕生② | 当初は諸々の危惧や弾圧を招きながらも、人びとの社交生活に欠くべからざるものとして着実に浸透していったコーヒーハウス。現代的観点からすれば、男性中心主義の最たるものを基盤としながらも、17世紀および18世紀という「時代」を味方にしながら確実に発展していった過程について、今日にも通じるところのある経済史的観点を交えつつご紹介していきたいと思います。 |
| 5 | 10/29 | イギリスの「近代」を拓いたコーヒー | 今日的観点からみれば、近代イギリスで大流行したコーヒーハウスには、外食産業としてあるまじき欠点がいくつかあったように思います。しかしそれゆえに、イギリスの「コーヒーハウス」からは近現代のイギリス社会を支えるさらなる独自組織が多々誕生しましたし、その反面、コーヒーハウス自体は衰退と消滅を免れず、別形態に変容せざるを得なかったのも事実です。イギリスの「近代」を確かに切り拓きながら、最終的に消滅せざるを得なかったコーヒーハウスの功と罪に思いを馳せます。 |
| 6 | 11/05 | コーヒーから紅茶へ:移り変わる流行① | コーヒーハウスの欠点をことごとく補うかのように登場し大流行したのが、紅茶専門店もしくはコーヒー、紅茶その他の娯楽を提供する「プレジャー・ガーデン」と呼ばれる遊興施設です。今日の日本の感覚からいえば、千葉方面のいわゆる「夢の国」的立場にあったそれらの施設の詳細を学ぶことで、イギリスがコーヒーから紅茶の国へと次第に移行していった経緯の一端を理解したいと思います。 |
| 7 | 11/12 | コーヒーから紅茶へ:移り変わる流行② | 近代イギリスにおいて、国民的飲料として紅茶がコーヒーにとってかわった背景には、同時代の帝国主義的政策の成功があったことは否めません。嗜好品の輸出入における不公正という永遠の課題を、主として18世紀から19世紀にかけてのイギリス帝国のありようを例に、あらためて真摯に考えてみたいと思います。 |
| 8 | 11/19 | 紅茶がもたらした二つの戦争① | 近代イギリス帝国の最も大きな綻びのひとつがアメリカの独立にあったことは周知の事実で、その直接の引き金となったのが「紅茶(=ボストン・ティーパーティー事件)」であったことも、比較的よく知られているのではないでしょうか。しかしながら、そこにいたるまでにも既に紅茶の輸出入にまつわる目を覆いたくなるようなイギリス側の横暴や不正が多々あったことは、あまり知られていないかもしれません。イギリス史のダークサイドをも担う「茶」の取引の歴史について理解を深めます。 |
| 9 | 11/26 | 紅茶がもたらした二つの戦争② | 紅茶という観点から近代イギリス史のダークサイドを語るうえで、アメリカ独立以上に深刻な問題をはらんでいるのが、茶の最大の原産地であり輸入先であった中国との「アヘン戦争」でしょう。もしもイギリスが「紅茶の国」でなかったならば、起こらずに済んだかもしれないこの問題について、様々な観点から考察を深めます。 |
| 10 | 12/03 | 「紅茶の国」の美のかたち | 近代世界史上の大事件に発展するような問題をいちどならず引き起こすほどに、イギリスという国において欠くべからざるものとなった「紅茶」。その紅茶が、同国の芸術文化に影響を及ぼさないはずがなく、イギリス文学や美術は紅茶のモチーフには事欠きません。そのなかでも、第9回までで学んだ内容を目に見えるかたちで証しするような、美しい文章や絵画をご紹介したいと思います。 |
テキスト
テキスト
小林章夫『コーヒー・ハウス』(講談社学術文庫)(ISBN:978-4061594517)
講師紹介
- 齊藤 貴子
- 早稲田大学・上智大学大学院講師
- 早稲田大学教育学部英語英文学科卒、同大学院教育学研究科博士課程修了後、助手を経て現職。専門は近代イギリス文学・文化。主として詩と美術の相関を研究。『ラファエル前派の世界』(東京書籍)、『英国ロマン派女性詩選』(国文社)、『肖像画で読み解くイギリス史』(PHP研究所)、『イギリス恋愛詞華集―この瞬間を永遠に―』(研究社)など著訳書多数。




