ジャンル 現代社会と科学
早稲田校
石が語るアンコール遺跡
内田 悦生(早稲田大学教授)
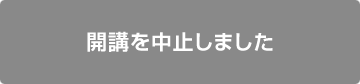
| 曜日 | 金曜日 |
|---|---|
| 時間 | 15:05~16:35 |
| 日程 |
全5回
・07月11日 ~
08月22日 (日程詳細) 07/11, 07/18, 07/25, 08/01, 08/22 |
| コード | 120740 |
| 定員 | 30名 |
| 単位数 | 1 |
| 会員価格 | 受講料 ¥ 14,850 |
| ビジター価格 | 受講料 ¥ 17,077 |
目標
・アンコール遺跡を含むクメール遺跡の歴史的背景や地理的分布について学ぶ。
・主要な石材の種類やその特性を活用した遺跡の建造順序の推定方法を理解する。
・石材の供給源や運搬経路について学ぶ。
・遺跡の崩壊および石材の劣化要因について理解する。
・石材劣化調査における非破壊検査手法について学ぶ。
講義概要
アンコール遺跡は、東南アジア最大級の石造建造物であるアンコール・ワットを含む遺跡群の一つであり、9〜15世紀にクメール人(現在のカンボジア人)によって建造された。この時期にクメール人が築いた遺跡は総称して「クメール遺跡」と呼ばれ、カンボジアを中心にタイやラオスにも分布している。本講座では、特にアンコール遺跡に焦点を当て、建造に使用された石材の研究を通じて明らかになった遺跡建造の謎を紹介する。また、15世紀以降、自然の営力により遺跡の崩壊や石材の劣化が進んでおり、その要因や石材の非破壊調査法についても解説する。
各回の講義予定
| 回 | 日程 | 講座内容 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 07/11 | クメール遺跡の概要 | クメール人(カンボジア人)によって9世紀〜15世紀にかけて建造された石造(一部レンガ造)の建造物群は「クメール遺跡」と呼ばれ、その代表がアンコール・ワットを含むアンコール遺跡である。クメール遺跡はカンボジア、タイ、ラオスにかけて広がっており、大小合わせて数千の遺構が存在するといわれている。本講義では、まず東南アジアおよび日本の石造文化財を紹介し、その後、アンコール遺跡をはじめとする主要なクメール遺跡を紹介する。 |
| 2 | 07/18 | アンコール遺跡の砂岩について | 講義のはじめに、アンコール遺跡の概要を紹介するビデオを上映する。続いて、アンコール遺跡において多用されている灰色砂岩に着目し、その磁性や各種特徴をもとに、各寺院の建造時期や建造順序がどのように決定されるかを解説する。 |
| 3 | 07/25 | アンコール遺跡のラテライトとレンガの話および砂岩材の石切り場と運搬経路 | アンコール遺跡では、砂岩以外にもラテライトや焼成レンガが使用されている。本講義では、砂岩に次いで重要な石材であるラテライトについて解説するとともに、古い時代の寺院に使用されているレンガについて紹介する。また、主要な石材である灰色砂岩の石切り場やその運搬経路について解説する。 |
| 4 | 08/01 | 遺跡崩壊および石材劣化機構 | アンコール遺跡は、15世紀に隣国のアユタヤ朝によって制圧された。その後、一部の寺院は信仰の対象となっていたものの、次第に放棄され、自然の営力によって崩壊が進むとともに、石材劣化も引き起こされた。本講義では、このような遺跡崩壊および石材劣化の要因について解説する。 |
| 5 | 08/22 | 石材の非破壊調査法 | アンコール遺跡はユネスコの世界文化遺産に登録されており、石材そのものやその劣化に関する調査を行うにあたっては、非破壊であることが求められる。そこで、本講義では、石材およびその劣化の調査において、どのような非破壊調査が実施されているかについて解説する。 |
ご受講に際して(持物、注意事項)
◆休講が発生した場合の補講日は、8月29日(金)を予定しています。
講師紹介
- 内田 悦生
- 早稲田大学教授
- 理学博士(東京大学)。専門分野は「岩石・鉱物・鉱床学」並びに「文化財科学」。現在の研究テーマは「花崗岩に基づく東南アジアの地質構造発達過程の解明と鉱床生成との関係の解明」および「アンコール遺跡をはじめとしたクメール遺跡の建造に関する謎の解明並びに石材劣化機構の解明」。主要著書:岩石・鉱物のための熱力学 共立出版;石が語るアンコール遺跡 早稲田大学出版部:地球・環境・資源 - 地球と人類の共生をめざして 共立出版 編著。




