ジャンル 芸術の世界
オンライン
グローバル美術史に向けて、日本の近代美術史を問い直す
稲賀 繁美(京都精華大学教授)
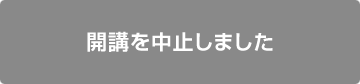
| 曜日 | 火曜日 |
|---|---|
| 時間 | 13:00~14:30 |
| 日程 |
全10回
・04月01日 ~
06月17日 (日程詳細) 04/01, 04/08, 04/15, 04/22, 05/13, 05/20, 05/27, 06/03, 06/10, 06/17 |
| コード | 710402 |
| 定員 | 30名 |
| 単位数 | 2 |
| 会員価格 | 受講料 ¥ 29,700 |
| ビジター価格 | 受講料 ¥ 34,155 |
目標
・「常識を豊かにする教養講座」ではなく、従来の枠組みを問い直す問題意識を発火させたい。
・「定説」のうらに隠された「歴史」の生成される現場に迫りたい。
・美術館や博物館を訪れる際の、「新たな発見」への糸口を養いたい。
講義概要
19世紀後半の西洋のフランス近代美術といえば、印象派の兄貴分であったマネから印象派、さらには後期印象派あるいは脱印象派と呼ばれる系譜が、常識として通用しています。そこに日本の近代美術がどのように関わっていたのかを、本講座では問い直します。19世紀後半の欧米では日本趣味現象、いわゆるジャポニスムが発生しますが、ちょうどその時期に日本美術は近代へと目覚めたといわれます。それではその両方の潮流はどのように交わったのか、それを探求してゆく講座です。そして講座の最後には、これらの話題を土台として、あらたなグローバルな美術史にむけた構想を提案します。
各回の講義予定
| 回 | 日程 | 講座内容 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 04/01 | エドゥアール・マネ《草上の昼食》と1863年の「スキャンダル」探訪 | エドゥアール・マネ《草上の昼食》は1863年のパリの歴史的な「落選者展」で「スキャンダル」を起こした、といわれてきました。しかしそれは果たして、歴史上の事実だったのでしょうか?この近代絵画史の開幕を告げる逸話の「神話」を解剖します。 |
| 2 | 04/08 | 「落選者展」からも「落選」してみせた作品の運命 | 前回の「落選者展」にも展示できない作品をわざと制作した画家がいます。それはマネより一回り年上のギュスターヴ・クールベでした。写実主義の巨匠といわれるクールベですが、その彼はどのような策略を練っていたのでしょうか?そのクールベの「たくらみ」の謎に迫り、従来の定説への挑戦も試みます。 |
| 3 | 04/15 | マネが真似た、北斎 | マネをはじめとする欧州の画家たちは、1860年代からは、日本の錦絵版画あるいは浮世絵を呼ばれる木版画の感化を受けるようになります。今日ではすでによく知られた話題ですが、しかしそこにはまだ 学会でも公認とはなっていない、さまざまな謎が隠されています。そもそも北斎は、どうして欧州で、日本を代表する藝術家へと出世したのか。その背景を探ってゆきます。そこには、江戸時代後期に西欧から中国・蘇州経由で日本に移入された透視図法も関わっていたことが見えてきます。 |
| 4 | 04/22 | 陶磁器・工藝のジャポニスム | 浮世絵版画が西洋の藝術家に大きな影響を与えた、との通説があります。しかし実際には、ジャポニスムはむしろ、陶磁器や装飾美術の領域で展開しました。とりわけそこでフランスの批評家や藝術家が注目したのが「琳派」でした。今回は、世紀末のエミール・ガレや、彫刻家のオーギュスト・ロダン、20世紀に晩年を迎えるクロード・モネに至る藝術家たちが、いかに日本の陶磁器や装飾屏風に感化されたのかを追ってみます。そもそも、どうしてこの局面は、ながらく見落とされていたのでしょうか? |
| 5 | 05/13 | ファン・ゴッホの日本、ポール・ゴーガンのタヒチ | 日本でも人口に膾炙した、あまりに有名な二人の画家ですが、彼らの営みにも、なお多くの未解決の謎が孕まれています。ゴッホは日本に何を探したのか。ゴーガンはタヒチで何を見出したのか。そこには初期の欧米人日本探訪者や、小泉八雲として知られるラフカディオ・ハーンも絡まってきます。皆さんの常識を一新する新解釈、あらたな仮説を展開します。 |
| 6 | 05/20 | 岡倉天心とインド:ベンガル・ルネッサンスと日本 | いままで概観してきたジャポニスムと日本との関わりという文脈のなかに、『茶の本』で有名な天心・岡倉覚三を位置づけてみましょう。とりわけ、1901年から翌年にかけての岡倉のインド旅行に焦点を絞ります。この分野は近年、著しく解明が進みました。『東洋の理想』や『東洋の覚醒』として知られる英文著作は、どのような状況で書かれたものだったのでしょうか。従来の常識の塗り替えが試みられます。 |
| 7 | 05/27 | 柳宗悦「民藝」を同時代の世界に置き直す | 岡倉の衣鉢を継いだ美学者として、柳宗悦と民藝を取り上げます。 ここでも、とりわけ、同時代のインドにおける陶磁器の再評価と、宗悦の朝鮮における陶磁器への開眼とに注目します。日本のウイリアム・モリスなどとも呼ばれる柳の民藝運動を、同時代の世界史的な文脈のなかで再検討する試みです。 |
| 8 | 06/03 | 矢代幸雄とは誰だったのか? | 柳宗悦と同時代の美術史家で、西洋でも英文著書『ボッティチェルリ』(1925)で著名な、矢代幸雄を取り上げます。大著『日本美術の特質』の著者でもあった矢代は、晩年に『日本美術の再検討』にも挑みます。世界のなかで、日本美術のあり方に思索を巡らした矢代は、国際文化交流にも貢献した人物です。その今日的再評価を目指します。 |
| 9 | 06/10 | アフリカと日本の芸術的相互理解に向けて | アフリカの美術というと、何が思い出されるでしょうか?仮面や祭礼の飾り物は民族学博物館で見ることができますが、現代美術となると、日本ではまだ広くは知られていないのが現実です。そのなかで金属の織物を手掛けるエル・アナツイの創作に焦点をあててみます。アフリカを日本からみることで、従来の欧米基軸のアフリカ理解とは異なる三点測量の可能性を提唱します。 |
| 10 | 06/17 | あらたなグローバル・アート・ヒストリーに向けて | 昨今、「グローバル・ヒストリー」が説かれ、美術史でGlobal Art Historyへの志向が顕著です。最終回には、この方向に向かう現状を批判的に考察します。話題としては、フランスの文化大臣を勤めた文筆家のアンドレ・マルローとアフリカ美術、日本美術との関係を取り上げます。岡本太郎、加藤周一、高階秀爾といった日本を代表する知識人にも言及する予定です。あらたな「パラダイム」(その意味は講義で説明します)のもとで、従来の美術史概説のあり方の問い直しも提唱する所存です。 |
ご受講に際して(持物、注意事項)
◆休講が発生した場合の補講は、6月24日(火)を予定しております。
◆参考図書として『日本美術の近代とその外部』(稲賀 繁美著・ISBN:978-4-595-31859-7・放送大学教育振興会出版)をお読み頂くと講座への理解が深まります。
◆本稿は、いわゆるジャポニスム現象についての概論を提供するものではありません。むしろ従来の議論では欠落していた局面に照明をあて、それをグローバル・アート・ヒストリーと近年呼ばれるようになった潮流に、批判的に添わせる試みとなります。
◆Zoomウェビナーを使用したオンライン講座です。
◆お申込みの前に必ず「オンラインでのご受講にあたって」をご確認ください。
◆お申込みいただいた有料講座の動画は、当該講座実施の翌々日(休業日を除く)17:30 までに公開します。インターネット上で 1 週間のご視聴が可能です。視聴方法は、以下をご確認ください。
【会員】授業動画の視聴方法(会員向け)
【ビジター・法人会員】授業動
画の視聴方法(ビジター・法人会員向け)
講師紹介
- 稲賀 繁美
- 京都精華大学教授
- 広島育ち。博士(文学:パリ第7大学)。専門分野:比較文学・比較文化、文化交渉史、比較倫理。三重大学人文学部、国際日本文化研究センター・総合研究大学院大学定年退職後、京都精華大学国際文化学部に勤務、2025年3月で退任。放送大学客員教授・科目担当責任者。近著に『矢代幸雄』(日本評伝選・ミネルヴァ書房)、『美/藝術』(「日本の近代思想を読み直す」3 東京大学出版会)『跨文化学術行脚』(花鳥社)など。




