ジャンル 日本の歴史と文化
中野校
女帝からキサキへ 平安初期における王権構造を考える
仁藤 智子(国士舘大学教授)
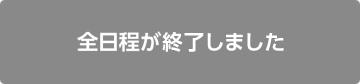
| 曜日 | 月曜日 |
|---|---|
| 時間 | 13:10~14:40 |
| 日程 |
全2回
・04月21日 ~
05月12日 (日程詳細) 04/21, 05/12 |
| コード | 310202 |
| 定員 | 36名 |
| 単位数 | 1 |
| 会員価格 | 受講料 ¥ 5,940 |
| ビジター価格 | 受講料 ¥ 6,831 |
目標
・平安時代の歴史に対する理解を深める。
・多角的な視野や視点から歴史を考える力を養う。
講義概要
平安時代の皇位継承は、「藤原氏の陰謀説」で語られることが多かったのではないでしょうか。しかし、主語を天皇あるいは王権とすると、通説とは違う歴史の側面を見ることができます。本講座では、このような視角から、古代における女帝(女性天皇)の終焉や天皇の配偶者であるキサキの変質の過程から、平安初期(九世紀)における幼帝の出現やいわゆる「摂政」「関白」の発生を再検討します。第1回は、女帝の終焉はどのように起きてきたのか、井上廃后から承和の変まで取り上げます。第2回は、女帝や皇后不在の時代における幼帝の出現や、「摂政」発生の契機となった応天門の変を中心に、王権構造の変質を紐解いてまいります。
各回の講義予定
| 回 | 日程 | 講座内容 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 04/21 | 女帝の終焉 | 770年に没した称徳女帝のあと、次の女帝の出現は、江戸時代(明正天皇と後桜町天皇)まで待たなければなりませんでした。しかし、その間女帝が封印されていたわけではなく、その可能性は内包されたままであったことが歴史学の成果として得られています。今回の講義では、①日本古代において女帝とはどのように出現しえたのか、②称徳女帝の後、井上廃后事件(772年)から承和の変(842年)までの間に、王権内部でどのような葛藤があったのかを明きらかにします。そのうえで、③古代的な女帝が終焉した要因を考えていきたいと思います。 |
| 2 | 05/12 | 幼帝の出現とキサキの変質 | 女帝の終焉と平安初期に模索された複数王統の迭立の収斂によって、仁明系王統が皇位継承を担う唯一の王統となります。その結果、天皇の若い死によって、幼帝の登場を余儀なくされました。今回の講義では、天皇の配偶者としてのキサキに焦点を当てて、①女帝や女系天皇を忌避する過程で、キサキの在り方がどのように変化したのか、さらに②幼帝の出現(858年)によって、誰が幼帝を補佐、輔弼するのか、③その結果この時代独特の王権構造が模索され、のちの「摂政」関白]を生み出す契機となっていくことを明らかにしていきたいと思います。 |
ご受講に際して(持物、注意事項)
◆休講が発生した場合の補講日は、5月26日(月)を予定しております。
◆参考図書:『古代史講義』(佐藤信編、ちくま新書、2018年)。『天皇はいかに受け継がれたのかー天皇の身体と皇位継承』(績文堂、2019年)。『人物で学ぶ日本古代史3 平安時代編』(吉川弘文館、2022年)。『平安時代天皇列伝』(戎光祥出版、2023年)。『古代王権ー王はどうして生まれたのか』(岩波書店、2024年)など。
講師紹介
- 仁藤 智子
- 国士舘大学教授
- 博士(人文科学、お茶の水女子大学)。専門分野は日本古代史(王権論、比較王制史など)。主な研究業績として、『平安初期の王権と官僚制』(吉川弘文館)、「古代王権の由緒と正統性」(『古代王権』所収、岩波書店)、『日本史概説ー知る・出会う・考える』(北樹出版)、「女帝の終焉」、「応天門の変と『伴大納言絵巻』」などがある。





