ジャンル 日本の歴史と文化
オンライン
明治維新後の日本政治―近世身分制度の解体から帝国議会まで
三村 昌司(早稲田大学教授)
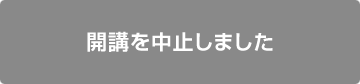
| 曜日 | 火曜日 |
|---|---|
| 時間 | 10:30~12:00 |
| 日程 |
全8回
・04月08日 ~
06月10日 (日程詳細) 04/08, 04/15, 04/22, 05/13, 05/20, 05/27, 06/03, 06/10 |
| コード | 710214 |
| 定員 | 30名 |
| 単位数 | 1 |
| 会員価格 | 受講料 ¥ 23,760 |
| ビジター価格 | 受講料 ¥ 27,324 |
目標
・江戸時代から明治時代にかけての社会の変化と政治の仕組みの変化について理解を深める。
・議事機関を日本に導入するときにどのような問題があったかを知る。
・歴史を知ることで、現代社会を俯瞰的に見る。
講義概要
明治維新は社会の大きな転換点でした。この講座では、明治維新から帝国議会開設までにあたる19世紀後半を主な対象として、日本における政治のあり方の変化をみていきます。ただし、「政治のあり方」といっても、明治維新前後に活躍した有名な偉人たち・政治家たちは、この講座にあまり出てきません。そうではなくて、政治の基盤になっていたシステムや、日本各地で政治に関わった「有名でない人」たちの活動を見ていきます。そのことを通じて、江戸時代から明治時代にかけて社会がどのように変わったか、理解してほしいと思っています。一風変わった明治の歴史を、知ってみませんか。
各回の講義予定
| 回 | 日程 | 講座内容 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 04/08 | 日本の近世社会の仕組み | 江戸時代は身分制の社会だったと言われます。そして、身分制は「士農工商」の社会だったとよく言われます。しかしそれは必ずしも正確な表現ではありません。そこで江戸時代の身分制がどのようなもので、それを基盤とした政治がどのようなものだったかを学びます。 |
| 2 | 04/15 | 明治新政府による議事機関の創設 | 大政奉還によって新たに成立した明治新政府は、自らの政治的正当性を示すために、江戸幕府とは異なった政治を行おうとしました。それが有名な「五箇条の誓文」に出てくる「公論」に基づく政治です。では、「公論」に基づく政治を行うために明治新政府は具体的にどのような仕組みを作ろうとしたのでしょうか。 |
| 3 | 04/22 | 公議所の実態と公議人の苦労 | 明治新政府は「公論」に基づく政治を実現するために、試行錯誤を繰り返します。そのなかで1869年に開設されたのが公議所でした。しかしこの公議所は、新政府の思惑どおりには機能しませんでした。全国各地から集まった公議人という公議所の議員に焦点をあてて、その様子を探ります。 |
| 4 | 05/13 | 会議による政治は地方へ(1)―地方民会と多数決の導入 | 近代的な議会で政治的な意思決定をするさいには、多数決がつきものです。現在の私たちは、それを当たり前のように受け入れています。しかし、多数決による政治的意思決定は、日本でいつごろから定着したのでしょうか。実はそのことは、江戸時代から明治時代にかけての社会の変化ともかかわっています。その様子を見ていきましょう。 |
| 5 | 05/20 | 会議による政治は地方へ(2)―柏崎県を例に | 明治新政府が掲げた「公論」による政治は、国レベルだけではなく地方レベルでも実現が目指されました。しかしその制度は一様ではなく、地域によって様々な試みがなされました。ここでは柏崎県(現在の新潟県)でつくられた「郡中議事者」という制度を主に取り上げて、地方レベルでの「公論」政治の構想と実態をみていきます。 |
| 6 | 05/27 | 新しい政治メディアの台頭 | 「公論」による政治が社会のなかに広がっていくためには、メディアの役割も重要な意味をもっていました。具体的には、新聞と演説会です。このふたつのメディアがどのようなものだったのかを具体的に見ていきます。 |
| 7 | 06/03 | 激化する自由民権運動 | 明治10年代になると、自由民権運動が広がりをみせたこともあって、多くの人々は新聞や演説会を通じて政治的な意見を発信していきます。それは「公論」による政治が広がったとも言えますが、しかし思わぬ事態も招きました。そのひとつが、暴力的な行為をともなって政治的な要求を実現しようとする状況です。なぜこのようなことになってしまったのか、考えてみます。 |
| 8 | 06/10 | 大同団結運動から帝国議会の開設へ | 帝国議会が開設されることが決まっていた1890年(明治23)が近づいてくると、全国で政治運動が活発化してきます。この回では、その運動が社会の変化のあり方に裏打ちされていたことを示していきます。また、開設された帝国議会の様子についてもみていくことで、明治維新以来目指された「公論」政治の到達点がいかなるものだったかを考えます。 |
ご受講に際して(持物、注意事項)
◆休講が発生した場合の補講は、6月17日(火)を予定しています。
◆Zoomウェビナーを使用したオンライン講座です。
◆お申込みの前に必ず
「オンラインでのご受講にあたって」をご確認ください。
◆お申込みいただいた有料講座の動画は、当該講座実施の翌々日(休業日を除く)17:30までに公開します。インターネット上で1週間のご視聴が可能です。視聴方法は、以下をご確認ください。
【会員・法人会員】授業動画の視聴方法(会員・法人会員向け)
【ビジター】授業動画の視聴方法(ビジター向け)
講師紹介
- 三村 昌司
- 早稲田大学教授
- 1976年生まれ。専門は日本近代史、地域歴史資料学。神戸大学大学院文化学研究科修了。博士(学術)。著書に『近世・近現代 文書管理の歴史』(佐藤孝之と共著、勉誠出版、2019年)、『日本近代社会形成史―議場・政党・名望家』(東京大学出版会、2021年)など。




