ジャンル 現代社会と科学
早稲田校
加齢心理学ゼミナール―老化との上手な付き合い方を考える
倉片 憲治(早稲田大学教授)
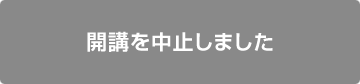
| 曜日 | 金曜日 |
|---|---|
| 時間 | 15:05~16:35 |
| 日程 |
全12回
・04月04日 ~
07月04日 (日程詳細) 04/04, 04/18, 04/25, 05/09, 05/16, 05/23, 05/30, 06/06, 06/13, 06/20, 06/27, 07/04 |
| コード | 110790 |
| 定員 | 20名 |
| 単位数 | 2 |
| 会員価格 | 受講料 ¥ 47,520 |
| ビジター価格 | 受講料 ¥ 54,648 |
目標
・テキストの輪読を通して、加齢に伴う心と体の変化を正しく理解できるようになる。
・学術論文の講読を通して、加齢変化に関する専門的でより深い知識と理解を得る。
・老化に対処する術(すべ)を身につけ、それを日常生活に応用できるようになる。
講義概要
「新版 老人の取扱説明書」をテキストとして加齢に伴う心と体の変化およびそれら加齢変化に対処する方法をゼミ形式で議論しながら学んでいきます。全12回のゼミ前半の回ではテキストを輪読形式で読んでいきます。ゼミ後半の回ではテキストの記述のもととなっている学術論文を一人1編ずつ選び順に読んでいきます。受講生の皆さんには前半に1回、後半に1回の計2回、テキストおよび論文の概要を紹介する発表者を担当していただきます。このように毎回のゼミをこなしていくことにより最終回に至る頃には独学では得られない老化と上手に付き合うための深い知識と技術が身につくことでしょう。
※春・夏学期を通して学びます。日程にご注意ください。
各回の講義予定
| 回 | 日程 | 講座内容 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 04/04 | ガイダンス:「加齢心理学」とは? | 本講座の中心テーマである「加齢心理学」とは、どのような学問でしょうか? その概要をご紹介するとともに、全12回のゼミの進め方についてガイダンスを行います。各回の発表の担当者および内容を受講生の皆さんと相談して決めますので、この回は必ず出席するようにしてください。 |
| 2 | 04/18 | 「新版 老人の取扱説明書」の輪読① | テキスト「新版 老人の取扱説明書」を、輪読形式で読み進めていきます。受講生の皆さん2〜3名に発表を担当していただき、それぞれ関心を持った章の概要を紹介していただきます。その発表を聴きながら、より深い理解を目指してゼミ全体で議論をしていきます。 |
| 3 | 04/25 | 「新版 老人の取扱説明書」の輪読② | 受講生の皆さん2〜3名に発表を担当していただき、それぞれ関心を持った章の概要を紹介していただきます。その発表を聴きながら、より深い理解を目指してゼミ全体で議論をしていきます。 |
| 4 | 05/09 | 「新版 老人の取扱説明書」の輪読③ | 受講生の皆さん2〜3名に発表を担当していただき、それぞれ関心を持った章の概要を紹介していただきます。その発表を聴きながら、より深い理解を目指してゼミ全体で議論をしていきます。 |
| 5 | 05/16 | 「新版 老人の取扱説明書」の輪読④ | 受講生の皆さん2〜3名に発表を担当していただき、それぞれ関心を持った章の概要を紹介していただきます。その発表を聴きながら、より深い理解を目指してゼミ全体で議論をしていきます。 |
| 6 | 05/23 | 「新版 老人の取扱説明書」の輪読⑤ | 受講生の皆さん2〜3名に発表を担当していただき、それぞれ関心を持った章の概要を紹介していただきます。その発表を聴きながら、より深い理解を目指してゼミ全体で議論をしていきます。 |
| 7 | 05/30 | 学術論文の講読① | 続いて、「新版 老人の取扱説明書」に引用された学術論文を読み進めていきます。受講生の皆さん2〜3名に発表を担当していただき、それぞれ関心を持った論文の概要を紹介していただきます。その発表を聴きながら、より深い理解を目指してゼミ全体で議論をしていきます。 |
| 8 | 06/06 | 学術論文の講読② | 受講生の皆さん2〜3名に発表を担当していただき、それぞれ関心を持った論文の概要を紹介していただきます。その発表を聴きながら、より深い理解を目指してゼミ全体で議論をしていきます。 |
| 9 | 06/13 | 学術論文の講読③ | 受講生の皆さん2〜3名に発表を担当していただき、それぞれ関心を持った論文の概要を紹介していただきます。その発表を聴きながら、より深い理解を目指してゼミ全体で議論をしていきます。 |
| 10 | 06/20 | 学術論文の講読④ | 受講生の皆さん2〜3名に発表を担当していただき、それぞれ関心を持った論文の概要を紹介していただきます。その発表を聴きながら、より深い理解を目指してゼミ全体で議論をしていきます。 |
| 11 | 06/27 | 学術論文の講読⑤ | 受講生の皆さん2〜3名に発表を担当していただき、それぞれ関心を持った論文の概要を紹介していただきます。その発表を聴きながら、より深い理解を目指してゼミ全体で議論をしていきます。 |
| 12 | 07/04 | まとめ | 全12回のゼミを振り返り、全体の議論のまとめを行います。さらに、加齢変化に対処するための日常生活での工夫やお店で見つけた“便利グッズ”などを各自紹介しながら、ゼミを通して新たに学び、考えたことをお互いに披露していきます。 |
ご受講に際して(持物、注意事項)
◆休講が発生した場合の補講は、7月11日、7月18日を予定しております。
◆老化や認知症の予防・治療を目的としたゼミではありません。
◆質問は随時受け付けますが、講座に関係が認められるものに限ります。
◆ゼミナール講座には、学びをより良いものにするための「グランドルール」があります。
相互に円滑に学びあうコミュニティづくりにご協力ください。
・議論の際には、他者の意見を否定するのではなく、建設的な意見を述べて議論を深めるようにする
・対等な立場で参加し、他者の意見や背景を理解する努力をする
・ゼミというコミュニティの中で、自分のできることを見出し、コミュニティへの貢献を意識して活動する
・ゼミに参加する全員で、ゼミ全体の「思考の質」、「成果の質」をあげることをめざす
テキスト
テキスト
平松 類『[新版]老人の取扱説明書』(SBクリエイティブ)(ISBN:978-4815612351)2017年に発行された、同じ書名の旧版があります。それと間違えないように、必ず[新版]をご用意ください。
講師紹介
- 倉片 憲治
- 早稲田大学教授
- 早稲田大学第一文学部心理学専修、卒業。国立研究開発法人産業技術総合研究所総括研究主幹を経て、2017年より現職。高齢者の心理特性に関する幅広い知見をもとに、年齢や障害の有無にかかわらず多くの人々に使いやすい製品、快適な環境の設計を考える「加齢人間工学」の研究・教育に従事。共著書に『バリアフリーと音』『アクセシブルデザイン 〜高齢者・障害者に配慮した人間中心のデザイン〜』『人間科学で読み解く幸せな認知症』など多数。




