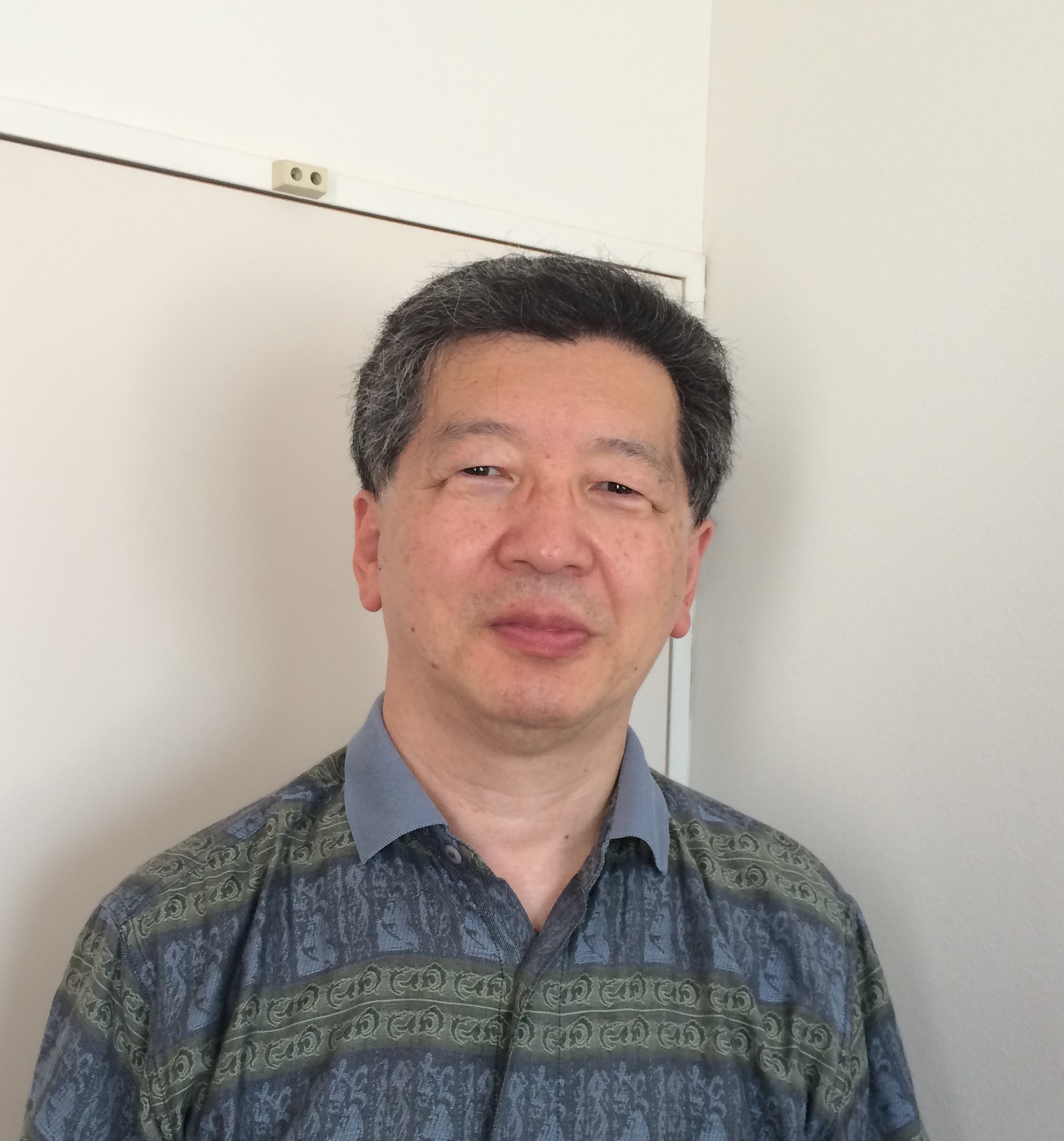ジャンル 日本の歴史と文化
早稲田校
「問い」を立てながら、戦後日本史を考える
成田 龍一(歴史学者、日本女子大学名誉教授)

| 曜日 | 金曜日 |
|---|---|
| 時間 | 13:10~14:40 |
| 日程 |
全6回
・04月18日 ~
06月13日 (日程詳細) 04/18, 05/09, 05/16, 05/30, 06/06, 06/13 |
| コード | 110264 |
| 定員 | 33名 |
| 単位数 | 1 |
| 会員価格 | 受講料 ¥ 17,820 |
| ビジター価格 | 受講料 ¥ 20,493 |
目標
・戦後日本史を、〈いま〉の観点から理解することを目指します。
・戦後日本の出来事と、その歴史的な意味を把握することを、目標とします。
・戦後日本史を学ぶことの重要さと面白さを、共有したいと思います。
講義概要
世界と日本は、いま、大きな激動のなかにあります。また、2025年は「戦後80年」ということも言われます。あらためて、歴史を振り返りながら、<いま>を検証することが試みられようとしています。折しも、高等学校に「歴史総合」という新しい科目ができ、これまでの歴史像が書き換えられています。「歴史総合」では、同時に「問い」を立てることの重要性が説かれます。「問い」を立てることによって歴史に向き合うのです。歴史を学ぶことは、たんに「事実」を学ぶのではなく、その意味を考えることなのです。今学期は、「問い」を立てながら、戦後日本史を考えてみましょう。「戦後80年」の歴史を、「問い」を立てながら学んでみます。
各回の講義予定
| 回 | 日程 | 講座内容 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 04/18 | はじめに 「問い」を立てるということ ――1945年8月15日は、いかなる意味で「戦後」の出発だったのだろうか | 歴史の教科書は、出来事=事実が淡々と記されているように見えます。しかし、その出来事が選び出され、説明されるにあたっては、教科書執筆者による「問い」が込められています――なぜ、この出来事が重要であるか、という「問い」です。「問い」を意識することによって、歴史をより深く理解できるはずです。そのことを、入り口として共有したいと思います。1945年8月15日は、いかなる意味で「戦後」の出発だったのでしょうか――この「問い」から出発します。 |
| 2 | 05/09 | 「敗戦」後の日本は、ゼロからの出発であったといえるだろうか | アジア・太平洋戦争の敗戦によって、日本本土は焼け野原となりました。「戦後」はその復興から始まり、ゼロからの出発と言われ、教科書でもそのように記されてきました。ハードの面――建物や工場、さまざまな施設は、確かに破壊しつくされてしまいました。しかし、政治の機構、官僚組織などソフトの面は残り、決してゼロからの出発とは言えないようです。「「敗戦」後の日本は、ゼロからの出発であったといえるだろうか」と「問い」を立てて考えてみます。 |
| 3 | 05/16 | 「戦後民主主義」とは、どのような民主主義であったのだろうか | 敗戦とともに、占領が始まります。連合国軍の占領のもとで、「非軍事化」と「民主化」といわれるさまざまな変革がなされます。治安維持法の廃止、農地改革や財閥解体、あるいは日本国憲法や教育基本法の公布・制定といったことがらです。このような動きの背景には、人々の戦争に対する反省があり、主体的な活動もなされました。現在では「戦後民主主義」と呼ばれるこの動きの意味を、思想家や文学者の発言を軸に考えてみます。 |
| 4 | 05/30 | 「高度経済成長」は、どのような経験をもたらしたのだろうか | 「戦後史」の大きな出来事のひとつは、いうまでもなく「高度経済成長」です。「高度経済成長」によって、人々の生活は大きく変わったといわれ、実際、同時代の人々もそのことを実感していました。しかし、いまでこそ懐かしく語られる「高度経済成長」の時代ですが、同時代の人々にとっては好ましい経験だけではありませんでした。あらためて、「「高度経済成長」は、どのような経験をもたらしたのだろうか」と「問い」を立てて、検証してみます。 |
| 5 | 06/06 | 「戦後思想」は、いつまで続いたといえるだろうか | 「高度経済成長」のあと、「経済大国」となる戦後日本ですが、バブルがはじけた後はながい不況の時期に入ります。「失われた30年」ということすらも言われ、現在にいたっています。こうしたなか、一貫して「戦後」を主導してきた思想―理念としての「戦後思想」も、あらたな挑戦を受けます。あらたな思想―理念として登場してきた「現代思想」を参照しながら、「戦後思想」について考えてみたいと思います。サブカルチャーの興隆も見逃せません。 |
| 6 | 06/13 | 「戦後80年」は、いったいどのような歴史であったのだろうか | 「戦後日本社会」の目標は、経済的には「戦前」の水準を復活することであり、その目的が達せられると、さらなる経済成長が追求されました。その過程で「もはや戦後ではない」と言われもしましたが、1985年に「戦後40年」が言われ、その後も「戦後50年」はおろか、とうとう「戦後80年」さえも言われる状況となっています。なぜ「戦後」ということが、ここまで言われるのでしょうか。「戦後80年」の出来事を学んだ目で、あらためて問いかけてみます。 |
講師紹介
- 成田 龍一
- 歴史学者、日本女子大学名誉教授
- 1951年生まれ。早稲田大学第一文学部卒業後、ひきつづき、大学院文学研究科で近現代日本史を学ぶ。博士(文学・早稲田大学)。著作に、『戦後史入門』(河出文庫)、『近現代日本史との対話』(2冊、集英社新書)、『歴史論集』(3冊、岩波現代文庫)などがある。