ジャンル 芸術の世界
中野校
芸術人類学入門―人と世界を媒介する「音楽」の力
小西 公大(東京学芸大学准教授)
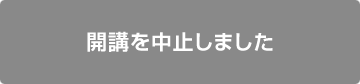
| 曜日 | 土曜日 |
|---|---|
| 時間 | 10:40~12:10 |
| 日程 |
全3回
・01月11日 ~
02月08日 (日程詳細) 01/11, 01/25, 02/08 |
| コード | 340415 |
| 定員 | 24名 |
| 単位数 | 1 |
| 会員価格 | 受講料 ¥ 8,910 |
| ビジター価格 | 受講料 ¥ 10,246 |
目標
・音楽とは何かという問題を、人類史的に捉え、理解を深める
・音楽と人類学との関係を理解する
・音楽のもつ力に関し、媒介と関与という概念を元に理解を深める
講義概要
本講義は、多様なアート世界の中でも「音楽」や「サウンド」のもつ力に着目し、人間の持つ能力の根源的な豊かさについて理解を深めていきます。そもそも音楽とは何か?という問題を、人類史的な視点をもって分け入り、近年の文化人類学における音楽研究の成果にも触れながら解き明かしていきましょう。本講義は、音楽をめぐる歴史や理論を概観しながら理解を深めていく座学的な側面と、実際に声や耳、身体を使って「音楽の力」を体感しながらその「媒介性」や「参与性」について体感していくワークショップも用意しております。
各回の講義予定
| 回 | 日程 | 講座内容 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 01/11 | 人類にとって音楽とは何か?:音楽人類学入門 | そもそも音楽とは何か、人類史的に音楽的なるものの現象と人間の関係を概観しながら、理解を深めていく。なぜ人類は音楽を必要としたのか、音楽はどのような場面で用いられてきたのか、身の回りの音楽について考えながら、音楽と人類学との関係を理解していく。 |
| 2 | 01/25 | 媒介の力:音楽すること(ミュージッキング) | 「音楽の力」をキーワードに、人類学的な音楽研究の新たな動向を学ぶ。特に「音楽すること(ミュージッキング)」概念が登場してから大きく転回した議論や、音楽という現象を捉えるための「媒介性」について学び、人間の持つ根源的な能力の豊かさについて想いを馳せる。 |
| 3 | 02/08 | 「参与」する音楽:情動と身体がつくりだす生成の場 | 音楽という現象が巻き起こしてしまう「参与」「はみ出し」「巻き込まれ」といった状況を、具体的な民族音楽を事例に学び、実際に身体や声、耳などを使ったワークショップで体感していただく。 |
ご受講に際して(持物、注意事項)
◆参考図書として、『そして私も音楽になった:サウンド・アッサンブラージュの人類学』(うつつ堂)をお読みいただくと、より理解が深まると思います。
講師紹介
- 小西 公大
- 東京学芸大学准教授
- 千葉県生まれ。博士(社会人類学)。専門は社会人類学、南アジア地域研究。インドや日本の離島をフィールドに、アートや芸能、音楽のもつ力を通じた社会空間の創造に関する研究を進めている。代表的著作物として『そして私も音楽になった:サウンド・アッサンブラージュの人類学』(2024年、編著、うつつ堂)などがある。





