ジャンル 日本の歴史と文化
オンライン
深遠なる日本食の旅路―味わいと料理の歴史をたどる
東四柳 祥子(梅花女子大学教授)
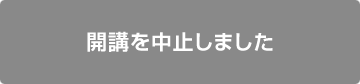
| 曜日 | 木曜日 |
|---|---|
| 時間 | 15:30~17:00 |
| 日程 |
全8回
・10月03日 ~
12月05日 (日程詳細) 10/03, 10/10, 10/17, 10/24, 11/14, 11/21, 11/28, 12/05 |
| コード | 730209 |
| 定員 | 30名 |
| 単位数 | 1 |
| 会員価格 | 受講料 ¥ 23,760 |
| ビジター価格 | 受講料 ¥ 27,324 |
目標
・日本人の食生活の歴史に対する理解を深める。
・日本食の独自性について、自分の言葉で説明できる力を身につける。
講義概要
いまや世界中で人気を博している日本食。訪日外国人の間で話題になるばかりでなく、海外諸国においても、日本食レストランの店舗数は堅調に増加しています。国境を超えて愛される日本食の特質を探るため、本講義では旧石器時代から現代までの日本人の食生活の軌跡を概観し、それぞれの時代において重要な料理形式、食材、菓子などの歴史的意義について解説します。日本食のたどってきた系譜を通覧し、未来に伝えるべきストーリーと魅力について、一緒に考えてみましょう。
各回の講義予定
| 回 | 日程 | 講座内容 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10/03 | 授業ガイダンス 日本の食生活史① | 旧石器時代、縄文時代、弥生時代、古墳時代、奈良時代の食生活事情について解説します。 |
| 2 | 10/10 | 日本の食生活史② | 平安時代、鎌倉時代、室町時代の食生活事情について解説します。 |
| 3 | 10/17 | 日本の食生活史③ | 安土桃山時代の食生活事情について解説します。 |
| 4 | 10/24 | 日本の食生活史④ | 江戸時代の食生活事情について解説します。 |
| 5 | 11/14 | 日本の食生活史⑤ | 明治時代の食生活事情について解説します。 |
| 6 | 11/21 | 日本の食生活史⑥ | 大正時代、昭和時代(終戦まで)の食生活事情について解説します。 |
| 7 | 11/28 | 日本の食生活史⑦ | 昭和時代(戦後直後から高度経済成長期頃まで)の食生活事情について解説します。 |
| 8 | 12/05 | 日本の食生活史⑧ まとめ | 昭和時代(1970年代以降)、平成時代、令和時代の食生活事情について解説します。また総括として、日本食の未来について考えます。 |
ご受講に際して(持物、注意事項)
◆休講が発生した場合の補講は12月12日(木)を予定しています。
◆Zoomウェビナーを使用したオンライン講座です。
◆お申込みの前に必ず「オンラインでのご受講にあたって」をご確認ください。
◆お申込みいただいた有料講座の動画は、当該講座実施の翌々日(休業日を除く)17:30 までに公開します。インタ
ーネット上で 1 週間のご視聴が可能です。視聴方法は、以下をご確認ください。
【会員】授業動画の視聴方法(会員向け)
【ビジター・法人会員】授業動画の視聴方法(ビジター・法人会員向け)
講師紹介
- 東四柳 祥子
- 梅花女子大学教授
- 石川県生まれ。博士(学術、国際基督教大学)。専門分野は、比較食文化論。現職のほか、(一社)和食文化国民会議調査・研究部会幹事、(一社)日本家政学会食文化研究部会委員、農林水産省や文化庁の食文化関連の委員会の委員などを務める。主な著書に『料理書と近代日本の食文化』(単著/同成社)、『近代料理書の世界』(共著/ドメス出版)、『日本の食文化史年表』(共編/吉川弘文館)などがある。




