ジャンル 日本の歴史と文化
早稲田校
「くずし字」はなぜ読めないのか 忘れられた文字・表記の一モード
岡田 一祐(慶應義塾大学准教授)
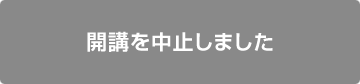
| 曜日 | 月曜日 |
|---|---|
| 時間 | 13:10~14:40 |
| 日程 |
全8回
・09月30日 ~
12月02日 (日程詳細) 09/30, 10/07, 10/21, 10/28, 11/11, 11/18, 11/25, 12/02 |
| コード | 130249 |
| 定員 | 30名 |
| 単位数 | 1 |
| 会員価格 | 受講料 ¥ 23,760 |
| ビジター価格 | 受講料 ¥ 27,324 |
目標
・19世紀における文字・表記の変化を理解する
・19世紀における文字教育について理解する
・日本文化に対する理解を深める
講義概要
古文書が「くずし字」で書かれたとはよく聞きますが、なぜそれほど重要なのに現代義務教育では「くずし字」を教えなくなってしまったのでしょうか。本講義では、19世紀の文字教育や実際の文字・表記の変化を辿ることで、どのようにして「くずし字」が普通には読めない字へと変わっていったのかを考えます。
各回の講義予定
| 回 | 日程 | 講座内容 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 09/30 | 「くずし字」は何に書かれていたか | 「くずし字」がなぜ読めないのかを考える前提として、社会のなかでどのような文章を書くために「くずし字」が使われていたのかを考えます |
| 2 | 10/07 | 「くずし字」によって語られたこと | 「くずし字」が用いられた文章ではどのような内容が語られていたのか考えます |
| 3 | 10/21 | 「くずし字」はどのように教えられたか | 寺子屋(手習塾)を代表に、「くずし字」がどのように教えられていたのかを考えます |
| 4 | 10/28 | 「くずし字」はどのように生まれたか(1) | 「くずし字」がどのように生まれたか、漢字の歴史から考えます |
| 5 | 11/11 | 「くずし字」はどのように生まれたか(2) | 「くずし字」がどのように生まれたか、日本語を書くことの歴史から考えます |
| 6 | 11/18 | 「くずし字」に代わって教えられたもの | 明治時代に入って教育制度が変わって、「くずし字」の代わりとしてなにが教えられたのか考えます |
| 7 | 11/25 | 「くずし字」を用いずに語られたこと | 江戸時代・明治時代に「くずし字」を用いずに語られたことがなんであったか考えます |
| 8 | 12/02 | なぜ「くずし字」は読めないのか | これまでの内容を総括し、題名の問いへの答えを考えます |
ご受講に際して(持物、注意事項)
◆休講が発生した場合の補講日は12月9日(月)を予定しています。
◆「くずし字」読解能力を身につけるための科目ではありません。「くずし字」を読めないが関心のある方も歓迎いたします。
講師紹介
- 岡田 一祐
- 慶應義塾大学准教授
- 千葉県出身。博士(文学、北海道大学)。専門分野は日本語学(日本語史)およびデジタル人文学。北海学園大学講師等を経て慶應義塾大学准教授。著書に『近代平仮名体系の成立: 明治期読本と平仮名字体意識』(文学通信)等。




