ジャンル 日本の歴史と文化
オンライン
芭蕉自筆の『奥の細道』から知る俳諧の真髄
魚住 孝至(放送大学特任教授)
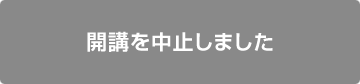
| 曜日 | 火曜日 |
|---|---|
| 時間 | 15:30~17:00 |
| 日程 |
全8回
・10月15日 ~
12月03日 (日程詳細) 10/15, 10/22, 10/29, 11/05, 11/12, 11/19, 11/26, 12/03 |
| コード | 730202 |
| 定員 | 30名 |
| 単位数 | 1 |
| 会員価格 | 受講料 ¥ 23,760 |
| ビジター価格 | 受講料 ¥ 27,324 |
目標
・芭蕉自筆本の内容と作品完成に籠めた芭蕉の思いを考える。
・芭蕉の奥羽行脚の実際を知り、「不易流行」の思想を考える。
・『おくのほそ道』の構成と主題を理解し「軽み」の展開を考える。
・俳諧を不易の文藝に高めんとした芭蕉の生涯とその後の展開を知る。
講義概要
1996年芭蕉自筆の『奥の細道』が発見された。76枚もの貼紙で修正し全て書き換えた頁もある。さらに修正を加え、書家の清書により完成した現行版では分からなかった芭蕉の意図が、自筆本から解明できる。芭蕉46歳、150日余の奥羽行脚後、「不易流行」を語り、4年後に『奥の細道』を執筆、推敲を徹底した。その作品の構成と主題を考える。文藝作品としてフィクションも加え、『源氏物語』、『平家物語』、漢詩、西行などの表現を踏まえ、月日が巡る中で生きる人間のあはれを描く。芭蕉は執筆後、日常生活の美を詠む「軽み」を説き、臨終に清書写本を去来に託した。作品が古典となる過程と研究、翻訳の問題に触れ、本解明の意義を考える。
各回の講義予定
| 回 | 日程 | 講座内容 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10/15 | 芭蕉自筆本の衝撃、芭蕉の生涯の概観と俳諧の説明 | 芭蕉自筆本の内容を見るとともに、その後修正されて書家の清書によって完成された過程を知る。改行見落としや書家のよる用字の書き換えが判明した。 芭蕉の生涯を概観するとともに、俳句とは異なる俳諧の説明をする。 |
| 2 | 10/22 | 深川隠棲、旅と歌仙と紀行文ー蕉風の形成 | 芭蕉が独自な俳風となるのは、37歳で日本橋から深川の庵に隠棲して以降である。旦那衆相手の俳諧師を辞め、庵での侘びの生活を実践して不易の文藝を目指した。漢詩や日本の古典を読みながら、侘びの思いを漢詩調で句にした。41歳で旅をし、尾張の歌仙(36句の連句)で連衆を指導して侘びの文藝を成した、翌年江戸に戻って紀行文を著した。 |
| 3 | 10/29 | 奥羽行脚の実際、「不易流行」の思想 | 46歳で奥羽行脚をした。同行の曾良の日記や旅先の弟子の記録から旅の実際が分かる。陸奥では歌枕を探訪し、変貌で時の流行とともに残るものも見た。出羽では2000m近い月山に登り、雲上で日月の交替と眼下の景を見て「天地流行」を語った。加賀では若い俳人の死に驚き、曾良と別れた。旅後に語った「不易流行」の内容を考える。 |
| 4 | 11/05 | 撰集『猿蓑』と奥羽の紀行文の課題 | 旅後、近江の庵で人生回顧と西行につながる風雅論を書く。京都の去来・凡兆との歌仙が上首尾で、俳諧の基準となるべき撰集を企画した。「方丈記」をモデルに俳文も書いたが、奥羽での文は俳文篇の取り止めで掲載されなかった。撰集『猿蓑』は元禄4年に刊行されたが、奥羽の紀行文は課題となった。 |
| 5 | 11/12 | 旅後4年を経て執筆、修正を重ね、書家の清書で『おくのほそ道』完成 | 2年ぶりに江戸に戻ると、点取俳諧の流行で愕然とする。半年後深川に新築の芭蕉庵に拠って独自な風を深めた。半年後結核が重くなった甥を庵に引取って看取った。元禄6年の盆、弟子の出入りを禁じて紀行文の執筆したらしい。10月頃自筆で清書したが、貼紙して修正を繰り返した。翌年4月書家の清書に「おくのほそ道」の題を付けて完成させた。 |
| 6 | 11/19 | 『おくのほそ道』の構成と主題 | 文と句を精査すると、陸奥・出羽など国ごとに月を書き分けた五部の構成が認められる。「予」の句は五十句で、自筆本の当初は、予の句と関係する曾良句を算入すると、四部が五十韻連句の数と同じで、最後に予の六句で結ぶ五部構成だった。五部で、「不易流行」を語り、各自は運命を受容すれば日常にも美が見出せるという主題が浮かび上がる。 |
| 7 | 11/26 | 『おくのほそ道』の文学的世界 | 紀行文は旅の情趣を書く文藝作品と芭蕉は考えていた。フィクションを加えた人物は虚名とし、その地は表記を変えた(早加、一ぶり他)。五部の部間で対照的な書き方をし、『源氏物語』『平家物語』漢詩、西行などの表現を踏まえて書く。「予」は旅の中で、王朝や中世とは異なる近世のあはれを見出し、西行に唱和して次の旅へと立つ。 |
| 8 | 12/03 | 『おくのほそ道』、不易の文藝へ | 生前弟子に作品を見せなかったが、臨終で去来に清書写本を譲る遺言をした。芭蕉没後8年、去来は出版して蕉門に渡した。弟子達は本作品で師の俳諧を改めて反芻し、芭蕉の句・文・俳論が集成された。没後77年『おくのほそ道』が再刊されて一般に知られて芭蕉は復興した。近現代に研究は大いに進展したが、自筆本の発見によって画期となる。 |
ご受講に際して(持物、注意事項)
◆休講が発生した場合の補講は、12月10日(火)を予定しています。
◆Zoomウェビナーを使用したオンライン講座です。
◆お申込みの前に必ず「オンラインでのご受講にあたって」をご確認ください。
◆本講座の動画は、当該講座実施の翌々日(休業日を除く)17:30までに公開します。インターネット上で1週間のご視聴が可能です。視聴方法は、以下をご確認ください。
【会員】授業動画の視聴方法(会員向け)
【ビジター・法人会員】授業動画の視聴方法(ビジター・法人会員向け)
講師紹介
- 魚住 孝至
- 放送大学特任教授
- 1953年生まれ。博士(文学)(東京大学)。国際武道大学教授を経て、2014年から放送大学教授。専門分野は日本思想・実存哲学。主要著書:『宮本武蔵-日本人の道』(ぺりかん社)、『芭蕉、最後の一句』(筑摩選書)、『哲学・思想を今考える』、『日本文化と思想の展開』(放送大学)など。




