ジャンル 現代社会と科学
オンライン
迫る核リスクをどうするか
吉田 文彦(長崎大学核兵器廃絶研究センター教授・センター長)
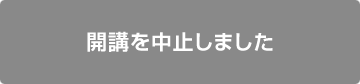
| 曜日 | 月曜日 |
|---|---|
| 時間 | 10:30~12:00 |
| 日程 |
全6回
・09月30日 ~
11月18日 (日程詳細) 09/30, 10/07, 10/21, 10/28, 11/11, 11/18 |
| コード | 730701 |
| 定員 | 30名 |
| 単位数 | 1 |
| 会員価格 | 受講料 ¥ 17,820 |
| ビジター価格 | 受講料 ¥ 20,493 |
目標
・核兵器のある世界の歴史と現状について理解を深める。
・これまで実際にあった核兵器使用のリスクについて知識を広める。
・これから懸念される新たな核兵器使用のリスクや核軍縮の役割について最新情報を知る。
講義概要
核戦争は起きないかもしれない。ただ、いつ起きるとも知れないリスクも存在する。世界に約1万発ある核兵器のうち約250発が都市攻撃に使われると、地球環境が変化して氷河期なみの寒冷化が起きるとの分析もある。確かに壊滅的打撃をどう避けるかは重要課題だが、そもそも核兵器は安全保障政策上、どのような役割を担っているのか。その中で核兵器使用のリスクとはどのようなものなのか。過去に実際にあった核戦争のニアミスはどれほど危険だったのか、今後考えられるリスクの高まりはどのようなものか。そして、リスクをどのように下げていけばいいのか。こうした疑問にわかりやすく答えて、核軍縮を含む今後の選択肢を示していく。
各回の講義予定
| 回 | 日程 | 講座内容 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 09/30 | 「核兵器のある世界」の歴史 | 1945年に核兵器が開発されて以降、核兵器の開発・保有・配備がどのように進んできたのか。核軍拡と核軍備管理(米ロ二国間と多国間の条約)はどのような関係を持ちながら、ここまできたのか。日米安全保障条約(日米安保)において米国の核兵器はどのように位置づけられ、どんな課題を抱えてきたのか。こうした問いに答える形で、「核兵器のある世界」の歴史を概括する。 |
| 2 | 10/07 | 核抑止とは何か:その効用と限界 | 核抑止が「成立」するために必要な「3条件」とは何なのか。核保有国はこれまで条件をすべて満たしてきたのか。核抑止が破綻して核兵器が使用されるリスクがあるのになぜ、核抑止は継続されてきたのか。継続の中で常に潜んできた危険とは何なのか。そもそも、第三次世界大戦が起きてこなかったのは、核抑止のおかげといえるのか。こうした問いに答える形で、核抑止の正体について解説する。 |
| 3 | 10/21 | 核兵器使用リスクが高まった過去の事例 | これまででもっとも核戦争のリスクが高かったとされる1962年の「キューバ危機」とはどのようなものだったのか。冷戦がひとつのピークに達した1983年には二度にわたって核戦争のリスクが高まる場面があったが、その実態はどのようなものだったのか。この他に、核兵器システムの機器の異常が原因で核戦争のリスクが一気に高まった事例には、どのようなものがあるのか。こうした問いに答える形で、実際に米ソ(米ロ)が経験した核戦争のニアミスついて説明する。 |
| 4 | 10/28 | ロシアによるウクライナ侵略のインパクト | ウクライナへのロシアの軍事侵略については複数の国際法違反が指摘されているが、具体的にどのような違反なのか。プーチン大統領らロシア政府首脳の言動が核抑止の「信頼性」「安定性」を脅かしているとの批判があるが、どのような理由に基づくものなのか。ウクライナ侵略でこれまでの「核のグローバルガバナンス」が大きく揺らいだとされるが、具体的にはどういうことなのか。こうした問いに答える形で、ウクライナ侵略が国際社会に与えたインパクトを解き明かす。 |
| 5 | 11/11 | 今後の新たな核兵器使用リスク | ロシアや中国、北朝鮮といった権威主義国家が冷戦後の核軍縮時代を打ち壊し、新たな核軍拡を進めている現状をどう考えればいいのか。AIやサイバーなどの新興技術の軍事利用拡大で、どのように核兵器使用リスクが高まりうるのだろうか。この歴史的な変化の時代に、核抑止についてどのような変化が想定されるのだろうか。こうした問いにそって、今後の新たな核兵器使用リスクを詳らかにしていく。 |
| 6 | 11/18 | 破滅回避のための核軍縮と日本の役割 | 人間は今後どのようにすれば、核兵器使用リスクを低下させて、破滅を回避していけるのだろうか。新たな核軍拡競争に歯止めをかけるものは何なのだろうか。破滅回避の試みにおいて、どのような核軍縮に期待がかかっているのだろうか。時計の針を核軍縮の時代へと戻していくために、唯一の被爆国である日本の役割とは何なのだろうか。こうした問いかけをしながら、解につながる選択肢を示していく。 |
ご受講に際して(持物、注意事項)
◆休講が発生した場合の補講日は11月25日を予定しております。
◆Zoomミーティングを使用したオンライン講座です。
◆お申込みの前に必ず
「オンラインでのご受講にあたって」をご確認ください。
◆お申込みいただいた有料講座の動画は、当該講座実施の翌々日(休業日を除く)17:30までに公開します。インターネット上で1週間のご視聴が可能です。視聴方法は、以下をご確認ください。
【会員】授業動画の視聴方法(会員向け)
【ビジター・法人会員】授業動画の視聴方法(ビジター・法人会員向け)
講師紹介
- 吉田 文彦
- 長崎大学核兵器廃絶研究センター教授・センター長
- 1955年京都市生まれ。東京大学文学部卒、朝日新聞社入社。ワシントン特派員、ブリュッセル支局長などを経て、2000年より論説委員、論説副主幹。その後は、国際基督教大学(ICU)客員教授、米国のカーネギー国際平和財団客員研究員など。2019年より、長崎大学核兵器廃絶研究センターのセンター長・教授。2017年より、英国Taylor & Francis社発行の国際学術誌「Journal for Peace and Nuclear Disarmament」の編集長。大阪大学にて博士号(国際公共政策)取得。主な著書は、『迫りくる核リスク』『核解体』『証言 核抑止の世紀』『核のアメリカ』。




