ジャンル 世界を知る
オンライン
キリスト教修道制とは何か―戒律とカリスマ
大貫 俊夫(東京都立大学准教授)
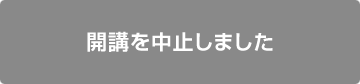
| 曜日 | 火曜日 |
|---|---|
| 時間 | 13:00~14:30 |
| 日程 |
全6回
・07月16日 ~
09月03日 (日程詳細) 07/16, 07/23, 08/06, 08/20, 08/27, 09/03 |
| コード | 720331 |
| 定員 | 30名 |
| 単位数 | 1 |
| 会員価格 | 受講料 ¥ 17,820 |
| ビジター価格 | 受講料 ¥ 20,493 |
目標
・さまざまな戒律とカリスマ修道士を通して中世キリスト教修道制の展開とその多様性を理解する。
・修道院と社会の相互交流の実態を通して、修道制がヨーロッパ中世社会の形成において果たした役割を知る。
講義概要
本講座では、古代地中海世界から中世後期にかけて発展したキリスト教修道制について、その原動力である戒律とカリスマ修道士の役割に注目しながら解説していく。その際、一次史料を読み解くことに重点をおき、社会によって受容され、時代によって変化する宗教的心性のありようについても詳しく扱うことにする。
各回の講義予定
| 回 | 日程 | 講座内容 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 07/16 | キリスト教修道制の起源─清貧と禁欲 | キリスト教修道制の起源は、ローマ帝国内でキリスト教が確立した3〜4世紀にさかのぼります。この頃に人々の共感を集めた清貧と禁欲の理念について解説します。 |
| 2 | 07/23 | エジプトの修道士たち─アントニオス、パコミオス、バシレイオス | 4世紀にエジプトの砂漠で厳しい修道生活を送ったアントニオス、パコミオス、バシレイオスについて解説し、修道制には隠修制と共住制という2つのタイプがあることを示します。 |
| 3 | 08/06 | 西欧修道制の確立─ヌルシアのベネディクトゥスとその『戒律』 | 歴史上、ラテン=キリスト教世界でもっとも強い影響力を有した修道戒律はヌルシアのベネディクトゥスによるものです。その内容と、それが普及した理由について解説します。 |
| 4 | 08/20 | 聖職者と修道士は何が違う?─アウグスティヌスとその『戒律』 | ラテン=キリスト教世界では、(在俗の)聖職者と修道士は違うカテゴリーに属しますが、アウグスティヌス戒律を通して聖職者も修道制の影響を強く受けるようになります。その歴史的な経緯を解説します。 |
| 5 | 08/27 | 修道会の「発明」─シトー会とクレルヴォーのベルナール | 修道会とは一体どのようなものでしょうか。12世紀におけるシトー会によるその「発明」の経緯と、シトー会の拡大におけるクレルヴォーのベルナールの役割について解説します。 |
| 6 | 09/03 | 托鉢修道会と都市社会─アッシジのフランチェスコとその『戒律』 | 都市社会に広がった托鉢修道会の歴史的意義について、アッシジのフランチェスコとその『戒律』を中心に解説します。 |
ご受講に際して(持物、注意事項)
◆休講が発生した場合の補講日は9月10日を予定しています。
◆Zoomウェビナーを使用したオンライン講座です。
◆お申込みの前に必ず
「オンラインでのご受講にあたって」をご確認ください。
◆お申込みいただいた有料講座の動画は、当該講座実施の翌々日(休業日を除く)17:30までに公開します。インターネット上で1週間のご視聴が可能です。視聴方法は、以下をご確認ください。
【会員】授業動画の視聴方法(会員向け)
【ビジター・法人会員】授業動画の視聴方法(ビジター・法人会員向け)
講師紹介
- 大貫 俊夫
- 東京都立大学准教授
- 1978年栃木県生まれ。東京大学文学部卒業。東京大学大学院人文社会系研究科修士課程修了。同・博士課程単位取得退学。2012年12月ドイツ・トリーア大学博士課程修了。Dr. phil.。岡山大学大学院社会文化科学研究科准教授を経て、2019年から首都大学東京(現東京都立大学)人文社会学部准教授。専門は中世ヨーロッパの宗教史、社会史、なかでもシトー会などキリスト教修道制と社会の関係史。著書にOrval und Himmerod. Die Zisterzienser in der mittelalterlichen Gesellschaft (bis um 1350)、監訳書に『中世ヨーロッパ:ファクトとフィクション』などがある。




