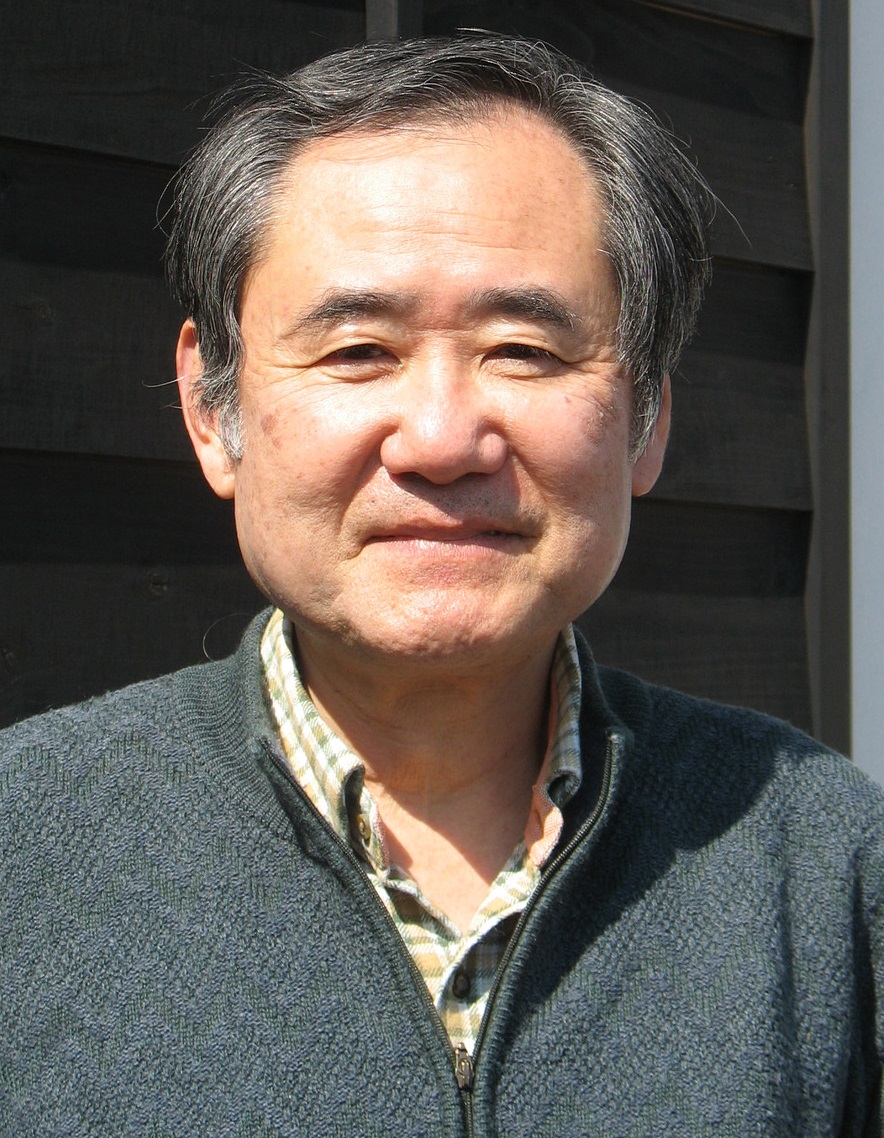ジャンル 日本の歴史と文化
早稲田校
西日本の戦国時代―安芸毛利氏を中心に
池 享(一橋大学名誉教授、日本史研究者)

| 曜日 | 火曜日 |
|---|---|
| 時間 | 13:10~14:40 |
| 日程 |
全6回
・10月15日 ~
11月19日 (日程詳細) 10/15, 10/22, 10/29, 11/05, 11/12, 11/19 |
| コード | 130253 |
| 定員 | 30名 |
| 単位数 | 1 |
| 会員価格 | 受講料 ¥ 17,820 |
| ビジター価格 | 受講料 ¥ 20,493 |
目標
・戦国争乱の歴史的意味について西日本を中心に考える。
・背景としての社会秩序や東アジア世界の変化に注目する。
・戦国大名の成立・展開過程を、安芸毛利氏を中心に理解する。
講義概要
西日本の戦国時代は、上杉謙信・武田信玄らが活躍する東日本に比べ、あまりよく知られているとはいえません。しかし、同じように戦国大名間の争乱が展開しただけでなく、日本海や東シナ海を介して朝鮮・中国などとの交流が盛んで、独自の特徴を持つ興味深い地域であり、後の江戸幕府による鎖国の意味を考える上でも重要な地域です。本講座では、西日本の戦国政治史をリードした安芸毛利氏の動向を中心に、東アジアや地域社会の変化、それにより引き起こされる紛争や戦乱、そこから生み出される戦国大名とその支配、さらに大名間の領土紛争や中央権力との連携・対立などを取り上げ、西日本の戦国時代の歴史的意味を考えたいと思います。
各回の講義予定
| 回 | 日程 | 講座内容 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10/15 | 戦国時代とは何か | 戦国時代は日本の「中世」から「近世」への移行期に位置し、文字通り戦乱がうち続く時代でしたが、何故そのような時代になったのでしょうか?普通は室町幕府の支配力が弱まったためと考えられがちですが、そもそも何故幕府の支配力が弱まったのかを、国家と社会の関係の変化という観点から考えたいと思います。それにより、この移行が単なる室町幕府から江戸幕府への政権交代ではなく、新しい社会・政治秩序が生み出される過程だったという見通しが得られるでしょう。 |
| 2 | 10/22 | 東アジアと地域社会の変化 | こうした国家と社会の関係の変化を生み出した要因は二つあります。大多数の人びとが日常生活を営む在地社会の変動が基本ですが、東アジア世界という日本を取り巻く広い地域の変動も重要です。特に海を通じて琉球・朝鮮・中国と隣接する西日本は、その影響を強く受けました。この二つの地域における15〜16世紀の社会変動の内容を具体的に検討し、それが戦国大名という新しい政治権力を生み出す見通しを得たいと思います。 |
| 3 | 10/29 | 安芸毛利氏の戦国大名化 | ここでは、西日本の戦国大名の代表といえる安芸毛利氏が、重臣井上衆の誅伐事件・周防陶氏との厳島合戦などを通じて、国人領主から戦国大名へと発展する過程を検討します。それにより、戦国大名がどのような社会的背景から生まれたのかを、明らかにしたいと思います。 |
| 4 | 11/05 | 大名領国の成り立ち | 戦国大名は、「公儀」として領国に臨み、法制定や行政・裁判制度の整備により政治秩序の強化を図るとともに、領主層を家臣として編成し軍事制度を整備しました。また、都市・流通支配などを通じて経済基盤の強化を図りました。西日本の特徴としてあげられるのは、東アジア各地との外交・貿易関係の展開です。ここでは、その具体的あり方を検討したいと思います。 |
| 5 | 11/12 | 「国郡境目相論」の展開 | 戦国大名が成立すると、隣接する大名間で領国支配圏をめぐる境界紛争(「国郡境目相論」)が起きるようになります。西日本では、毛利氏と出雲尼子氏・豊後大友氏の争いが軸となりますが、さらに伊予河野氏・備前浦上氏・肥前龍造寺氏などが関わり争乱は広域に展開します。また、南九州では薩摩島津氏、四国では土佐長宗我部氏の台頭が見られました。ここでは、それらを概観し、将軍による調停の意味も考えたいと思います。 |
| 6 | 11/19 | 織豊権力との連携・対立から統一政権への従属へ | 「国郡境目相論」の展開は、やがて中央の織田権力と連携・対立などの関わりを持つようになります。さらに、織田権力の畿内での勝利、東日本制圧を経て統一政権が成立し、西日本もその支配下に収められるようになり、「国郡境目相論」も終結しました。その後、豊臣秀吉の朝鮮侵略・徳川政権の鎖国政策により、西日本と東アジア諸地域との関係も大きく変化し、西日本の戦国時代が終結することになります。ここでは、その過程を概観し、全体のまとめとしたいと思います。 |
ご受講に際して(持物、注意事項)
◆休講が発生した場合の補講日は11月26日を予定しています。
◆参考図書として池享『毛利領国の拡大と尼子・大友氏』(吉川弘文館、ISBN978-4-642-06853-6)を挙げておきます。講義内容全体をカバーするものではありませんが、お読みいただけると理解に役立つと思います。
◆本講座は2022年度冬学期の講座「西日本の戦国時代―16世紀後半を中心に」と一部内容が重複しますが、内容は刷新されています。
講師紹介
- 池 享
- 一橋大学名誉教授、日本史研究者
- 1950年新潟市生まれ。一橋大学大学院を修了し経済学博士。新潟大学人文学部助教授、一橋大学経済学部教授などを歴任。専攻は日本中世史。主要著書に『大名領国制の研究』(校倉書房)、『日本中近世移行論』(同成社)、『動乱の東国史7東国の戦国争乱と織豊権力』(吉川弘文館)、『列島の戦国史6毛利領国の拡大と尼子・大友氏』(吉川弘文館)。